こんにちは。長壁です。
6月22日は満月になります。
満月の話題を聞くと思い出すこと
があります。
「赤くて丸い月を
“ストロベリームーン”っていうんだよ!」
子どもが私に教えてくれました。
さらに、絵を描いて見せてくれました。
みなさんも、こんな風に子どもから教えて
もらったことありますか?
理科の授業で、星や月について学習して
いたので、「こういう月があるんだ!」と驚い
たのと、知ったことを誰かに教えたい!と
いう思いからだったのでしょう。
子どもは学校の宿題で、月の観察があっ
たことを思い出しました。
観察して月の形と方角を書いていく内容
でした。
今思うと、学習したことを
「今日は満月だ!」「今日は三日月だ!」と
空を見て私に教えてくれていたのです。
「ストロベリームーン」はどういうときに
見えるのか?
せっかくなので、調べてみました。
「ストロベリームーン」とは?名前の由来は?
「ストロベリームーン」とは?
6月の満月を言うそうです。
なぜ、「ストロベリー」?
調べる前の私は、この時期の満月は
赤く見えるから赤い果実のいちごを
イメージしてなのかな?
なんて思っていました。
あながち間違ってはいないけど、
作物の収穫時期との関係があったのです。
名前の由来は、ネイティブアメリカンから
きているとのこと。
この頃はいちごの収穫期で、この時期の
満月を「ストロベリームーン」と呼ばれて
いる。
夏至の頃は、月が空の低い位置を通り、
地平線に近い位置にあるため赤く見える
そうです。
波長の短い青い光は大気を通りにくく、
波長の長い赤い光は大気を通過するので
私たちの目には赤っぽく見えるとのこと!
季節を確認するため?
英語の月の名前は、なぜ植物や動物など
が関係しているのでしょうか?
1月の満月を「ウルフムーン」と呼んだり、
2月の満月を「スノームーン」と呼んだりします。
昔の人たちは、季節を把握するために、
生活の基盤である農事や行事に関係する
動物や植物、イベントなどの名前をつけて
いたのですね。
満月の名前で、アメリカの先住民
ネイティブアメリカンの人たちの生活サイ
クルを知るきっかけにもなりますね〜。
親子で「インプット」と「アウトプット」で学びを!
「私も調べて知ったことを子どもに教えて
あげたいです。」
という話を社長にしたら、
社長から話題の『反転学習』という言葉を
聞きました。
反転学習とは、受講者が事前に自宅で予習したことをもとに、後日教室でディスカッションする授業形態のことです。
『反転学習とは | eラーニングと学びを考えるブログ』
予習でインプットしたことを、
授業でアウトプットするということですね。
私の場合、親子でお互いに知ったこと
(=インプット)を、相手に教えてあげる
(=アウトプット)ということですね。
学び合える親子関係を目指したきっかけ
でもあります。後は継続!
ただ、最近は、高校生の息子に頼ってます
(笑)
先日も、次男の携帯のデータの引き継ぎ
作業を全てやってくれましたー。
この少し前に、長男の携帯を買い替えるこ
とがありました。
そのときの手順を本人が操作しながら、
一緒に調べながら行いました。
そのとき行ったやり方を覚えていたという
のもあるのですが、
すっすっすっ!とこなしていて、わからない
ときはネットで調べながらやり、無事に
データの引き継ぎを完了しました。
「なんでそんなにスラスラできるの?」と
私が息子に聞いたら、「体が覚えてるから
かなぁ」と一言!
若いってすばらしい!!笑
私だったら、えーっと次はどうするんだっ
け??と頭で思い出すのに手こずりそうです
笑
親が全てをやってあげるのではなく、本人
にやらせてみて経験させるのは大切です
ね〜。
わからなかったら一緒に調べるという体験
は家庭でもできることだと改めて思いまし
た。
今度は、弟に教えてあげるのも兄弟ででき
る「反転学習」のひとつではないでしょうか。
ちなみに、満月の瞬間は6月22日(土)
10時8分頃。
天気次第ですが、前日の夜と土曜日の夜
にみなさんも、空を見あげてみてください。
参考サイト↓

【関連記事はこちらから】
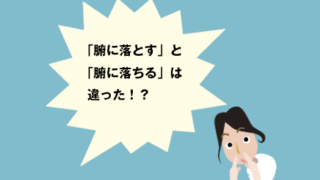
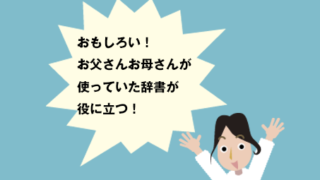
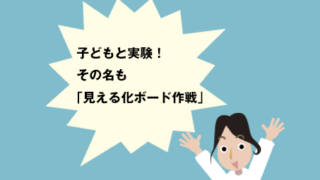


Comment